第069号 売上高と「売掛債権」「棚卸資産」から見る運転資本構造
今回は、私がコンサルティングを担当しているクライアント様の事例を、ご紹介したいと思います。
家電卸売業のS社は、社長を筆頭に営業力が高いという強みを持った組織ですが、その反面、管理力に弱みを抱えています。X5期も強みの営業力を活かし、売上高前年比10%アップの目標を見事に達成しましたが、社長は資金繰りに駆け回っている毎日です。
売上高、売掛債権、棚卸資産の前年対比を基に、運転資本構造のどこに問題があるのかを見ていきましょう。
売掛債権、棚卸資産の前年対比を基に、運転資本構造のどこに問題があるのかを見ていきましょう。
X4期 | X5期 | 前年比 | |
売上高 | 144,560 | 159,016 | 110.0% |
売掛債権 | 43,368 | 63,606 | 146.7% |
棚卸資産 | 7,077 | 9,200 | 130.0% |
まず、売掛債権について見ていきます。X4期の売掛債権回転期間(販売して回収するまでの期間)を求めてみましょう。
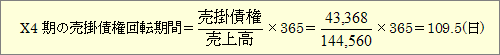
回転期間が同じであれば、売上が増えると、売掛債権は同じ割合で増えます。 ところがS社のX5期は、回転期間が146.0(日)に伸びています。
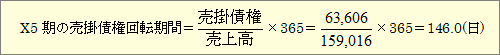
回転期間が伸びると、回転期間が同じ場合より、売掛債権が増加することになります。売上が上がれば仕入に対する支払いも増えるのが一般的ですから、S社のX5期の状況では、支払いに必要な現金が不足し、余分な資金を新たに調達しなくてはならなくなります。
つまりS社は、努力して売上を上げたにも関わらず、運転資本構造が悪化してしまったわけです。この原因はS社の売掛金管理にありました。売ることばかりに意識が偏り、売った後の売掛金の回収が疎かになっていたのです。その結果、売掛金の回収サイトが知らず知らずのうちに伸び、挙句の果てには貸倒れも出る始末でした。また、新しい取引先を増やしたいばかり、長い手形のサイトを受け入れてしまっていたことも原因のひとつでした。
次に、棚卸資産についてみてみましょう。棚卸資産も売掛債権と同様に、一般的には売上高に比例して増減するものです。ところが、S社の場合、売上が10%増えたのに対して、棚卸資産が30%と高い増加割合(※1)を示していました。これは、年度方針に掲げた「翌日配達による顧客満足の追求」を実現するために、在庫を増やしたことが原因でした。結果として、いわゆる「死に筋商品」を多種にわたって抱えざるを得なくなり、資金繰りを圧迫していたことが分かりました。
現在S社では、この状況の改善に向けて、次の対策を立て実行しています。
保有している売掛債権をチェックし、貸倒れの危険性が高い得意先を全件訪問。返済計画書の作成・提出の要求。
回収サイトの短い既存得意先の売上構成比を高める販売計画を立て、それ基づいた営業の実施。
一定金額以上の新しい掛け取引を始める際、必ず信用調査を実施。
仕入先に対する在庫の返品交渉。
自社在庫を低減するため、短納期の仕入先の開拓。
(※1)取引先の貸借対照表でこのような増え方をしているケースは、架空の在庫ではないかを疑ってみることが必要です。
お問い合わせ
ご相談はお気軽にご連絡ください。 メールは24時間365日受付しております。
